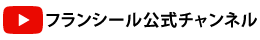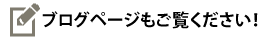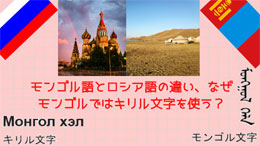お役立ち情報
日英翻訳の心得
日本語から英語に翻訳する際、訳文の品質を高めるために必要なスキルとは何でしょうか。
弊社のネイティブ翻訳者が、日英翻訳における心得をまとめました。
海外向けのレポートやレター等を英語に翻訳される皆様のお役にたてばと思います。
どうぞ参考にしてください。
弊社のネイティブ翻訳者が、日英翻訳における心得をまとめました。
海外向けのレポートやレター等を英語に翻訳される皆様のお役にたてばと思います。
どうぞ参考にしてください。
短文を心掛けること
通常、文は短いほど読みやすいものです。
英文では1文あたり20ワード以下となるのが理想的です。
また、日本語は英語に比べて長文になりがちですから、翻訳時に日本語1文を英語2文以上に分割したほうが良い場合もあります。
英文では1文あたり20ワード以下となるのが理想的です。
また、日本語は英語に比べて長文になりがちですから、翻訳時に日本語1文を英語2文以上に分割したほうが良い場合もあります。
受動態を避けること
英語ネイティブは明確な主語を持ち、かつ能動態(主語+動詞)の文を好みます。
基本的に受動態(主語+be動詞+過去分詞)は避けるべきでしょう。
和文に主語がない場合は、文脈から主語を導き出すのが一つの手です。
つまり、例えば調査に関する文であれば主語に"inspectors"を用います。
これにより、"it was confirmed in the inspection that・・・"という受動態の文章も、"inspectors confirmed that" と、より短く読みやすい文になります。
基本的に受動態(主語+be動詞+過去分詞)は避けるべきでしょう。
和文に主語がない場合は、文脈から主語を導き出すのが一つの手です。
つまり、例えば調査に関する文であれば主語に"inspectors"を用います。
これにより、"it was confirmed in the inspection that・・・"という受動態の文章も、"inspectors confirmed that" と、より短く読みやすい文になります。
名詞化を避けること
通常、英語では名詞よりも動詞(能動態)が好まれます。
例えば「分析する」という述部を翻訳する場合には、"conduct an analysis"とするよりも、シンプルに"analyze"としましょう。
例えば「分析する」という述部を翻訳する場合には、"conduct an analysis"とするよりも、シンプルに"analyze"としましょう。
文の順序とパラグラフの構成を考えること
英文の構成として好ましいのは、パラグラフの最初または最後の文は主題文になること、そして各パラグラフが持つトピックは1つになることです。
パラグラフが長い、あるいはパラグラフ内にトピックが複数ある場合は分割することを検討します。
パラグラフが長い、あるいはパラグラフ内にトピックが複数ある場合は分割することを検討します。
主語を一致させること
通常、パラグラフ内の主語は一つ(または複数だとしてもお互いに関連性がある主語)に絞るべきです。
主語を完全には統一できない場合も、できるだけそうなるように努力します。
主語を完全には統一できない場合も、できるだけそうなるように努力します。
情報を取捨選択すること
翻訳が不要な語句もあれば、行間を読んで翻訳する必要がある場合もあります。
重要な点は、日本語で書かれている内容をそっくりそのまま英語で伝達することで、日本語と英語で一語一語を一致させることではありません。
情報の取捨選択が、翻訳作業の大きなポイントになります。
重要な点は、日本語で書かれている内容をそっくりそのまま英語で伝達することで、日本語と英語で一語一語を一致させることではありません。
情報の取捨選択が、翻訳作業の大きなポイントになります。
句読法の違いを意識すること
日本語の強調表現でよく用いられるのは鉤括弧(「」)で、他に角括弧([ ])や山括弧()が使われる場合もありますが、英語では斜字、太字、下線、または大文字が頻繁に用いられます(つまり、MSワードの B(Bold: 太字) , I(Italic: 斜字) , U(underline: 下線 )ボタンをよく使います)。
引用符の違いを意識すること (” ”, 「 」、 など)
英語では引用元の文書や発言からそのまま引用される場合に限って引用符(” ”)が用いられますが、このため、日本語では引用符(括弧)が用いられていても、英語に翻訳する際には取り払ったほうが良い場合もあります。
脚注の使い方
日本語では脚注などを示す場合に「※」が使われます。
英語では、ページの終わりに脚注を設けるか、または"Notes:"に続く番号リストが使われます。
「※」を"*"に置き換えるのは必ずしも適切とは言えません。
英語では、ページの終わりに脚注を設けるか、または"Notes:"に続く番号リストが使われます。
「※」を"*"に置き換えるのは必ずしも適切とは言えません。
丸括弧に注意すること
丸括弧( )は、英語よりも日本語のほうがより頻繁に用います。
丸括弧で囲まれた語句を翻訳する場合は、括弧から取り出して本文内に含めるか、または独立した文にすることも検討したほうが良いでしょう。
丸括弧で囲まれた語句を翻訳する場合は、括弧から取り出して本文内に含めるか、または独立した文にすることも検討したほうが良いでしょう。
全角文字を残さないこと
全角文字(2バイトの文字)は英文に残さないほうが賢明です。
アジア言語のフォントがコンピューターにインストールされていない場合、表示の問題が発生することがあります。
残してしまいやすい2バイト文字の例として、丸括弧( )、アポストロフィ(‘)、コロン(:)、演算子(=)、数字(5や⑤)が挙げられます。
アジア言語のフォントがコンピューターにインストールされていない場合、表示の問題が発生することがあります。
残してしまいやすい2バイト文字の例として、丸括弧( )、アポストロフィ(‘)、コロン(:)、演算子(=)、数字(5や⑤)が挙げられます。
この他、英文を書くにあたってChicago Manual of Style(*)も参考になります。是非ご一読ください。
また、もし「やっぱり翻訳はプロにお願いしたい。」とのことでしたら弊社の翻訳サービスもご利用ください。自分で翻訳したけれど自信がない方にはネイティブチェックをお勧めしております。お気軽に弊社まで電話あるいはメールでお問合せください。
(電話 : 03-6908-3671, メール: info@franchir-japan.co.jp )
(*)Chicago Manual of Style:1906年にアメリカで出版された英文作成のためのスタイルガイド。2010年には16版まで発行されており、主に出版に携わる人が参考に使用。現在はオンライン版も。



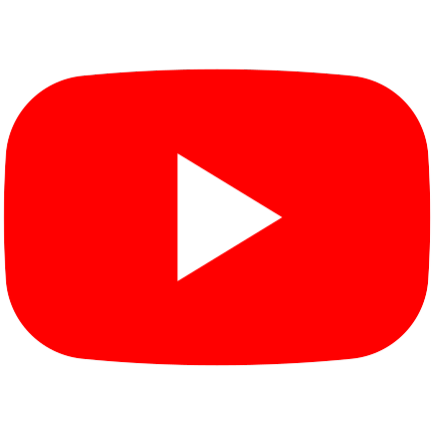
 お問い合わせ
お問い合わせ