皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年はコロナで大変でした。
しかしながら12月になるとさすがの師走。忙しくなってきました。
気づくとブログ掲載の数も少なくなっていて、日々の過ぎるスピードを感じます。
バタバタしているところへ、フランス語通訳の橋爪さんより再びマダガスカルの素敵な写真が届きました。
広がる田園風景や、お米が主食というところは、異国なのにどこか郷愁を感じます。(鍋)
************************
またマダガスカルの風景を送ります。
自分にとって忘れがたい風景ばかりです。
■まずパンガランヌ運河、

堂々とした川のように見えますが、フランスが、マダガスカルを植民地に併合した直後から、この運河の建設は、フランス人主導で始まりました。
■運河を行き交う人々

1897年のフランスによる植民地併合ですが、その頃、タマタブという大きな港から、マダガスカルの南方へ降りる道が無く、また海岸沿いにタマタブから南方方面へ船で下るには、大きな危険が伴いました。
潮流の乱れが激しく、また暗礁も多くあり、波浪が大きく、沿岸に沿って航行するのも相当な危険が伴いました。
そこで、フランス植民地の将軍が考え付いたのが、現に存在する多くの湖沼地帯や潟を貫き、南方方面へ下る運河を作ることでした。
■地図

タマタブからファラファンガーナまでの700km.
壮大なるインフラ建設でした。
マダガスカル支配のための仏軍移動のことも頭にあったでしょう。
現在では、700kmは航行できませんが、かなりの部分で修復を行い、運河近隣の人たちの足となり、手漕ぎのボート(ピローグ)や船外機付きの小型船で行き来しています。
また観光目的にもなり、ツーリストが小型船で行き交う姿も見受けられます。
■運河近くのホテルにて

■運河近くのレストランにて(タマタブ近郊)
(この写真は誰が撮ったの?そういうことは不問に付すことにしましょう。)

■お米の国 マダガスカル

水田風景です。タマタブの近郊です。
■水田風景です。

同じくタマタブ近くです。
水田は、マダガスカルはどこでも見られます。
1200mの高地の首都アンタナナリボにもたくさんあります。
苗代を作り、きちっと田植えをして、稲刈りも行います。
ただ、相当な田舎では、今でも、田植えをせず、直播きを行い、刈り入れは、穂積(ほづみ)を行っている農村もあります。
また水田耕作ではないオカボ(陸稲)を栽培していて、これも穂積を行っている地域もあります。
なにしろ、マダガスカル人は、お米さえしっかり食べられれば、幸せといった民族です。
一人年間平均100kg以上のお米を食べています。
(僕なんか、現在の日本で、2kgのパックをスーパーで買ってくると、
1か月間も食べていますから、現在の日本人はお米をあまり食べなくなったのでしょうね。)
■フォールドーファンの宿屋にて

お米を炊く前に、お米の中にある小石を取り除いているところです。
なにしろ、マダガスカルの農村では、お米のモミを路上で天日干しにします。
其の時にゴミや小石がモミに入り込んでしまいます。
なので、お米を炊く前には、必ず、小石取りを行います。
小石取りをした後は、お米は研ぎません。
小石取りのあとには、すぐ煮え立ったお湯の中にこのお米を入れて炊き始めます。
45分後には、炊き上がります。
■フォールドーファンの現場のワーカー用食堂です。

この洗面器みたいな大きな器に山盛りのご飯です。
肉と野菜を煮込んだものを汁と一緒にご飯にかけます。
これだけです。
いや、現地の人々にとって、これは結構な贅沢な食べ物です。
(現地の農村の家庭では、
野菜(キャッサバ、サツマイモ等の葉っぱ)に塩をいれて煮込み、それをご飯にかけて食べます。
肉や魚はご飯の中には見当たらないのがごく普通です。)
■奥の女性が盛っているご飯には、肉が見えるでしょう。

ご飯の量については、相当な量のように見受けられますが、実際、食べてみると、日本のご飯の方が、粘りとコシがあり、お腹にはこたえます。
マダガスカルのご飯は、ふわふわしていて、それほどお腹にもたれません。
■ 最後は、現地のワーカーさんたちのいる食堂風景です。

彼らと一緒に働いた3年間が懐かしく思い出されます。
本当に働き者の人たちばかりでした。
(橋爪)



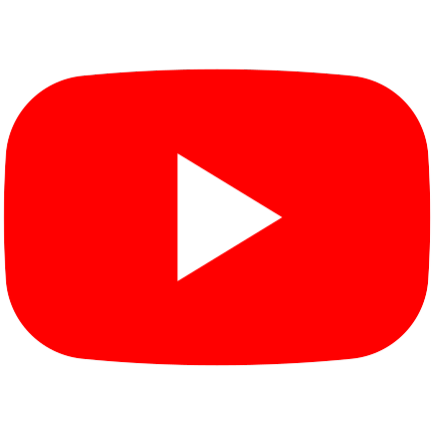
 お問い合わせ
お問い合わせ




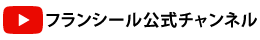


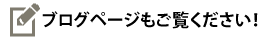




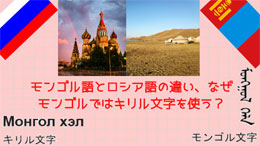



コメントを残す